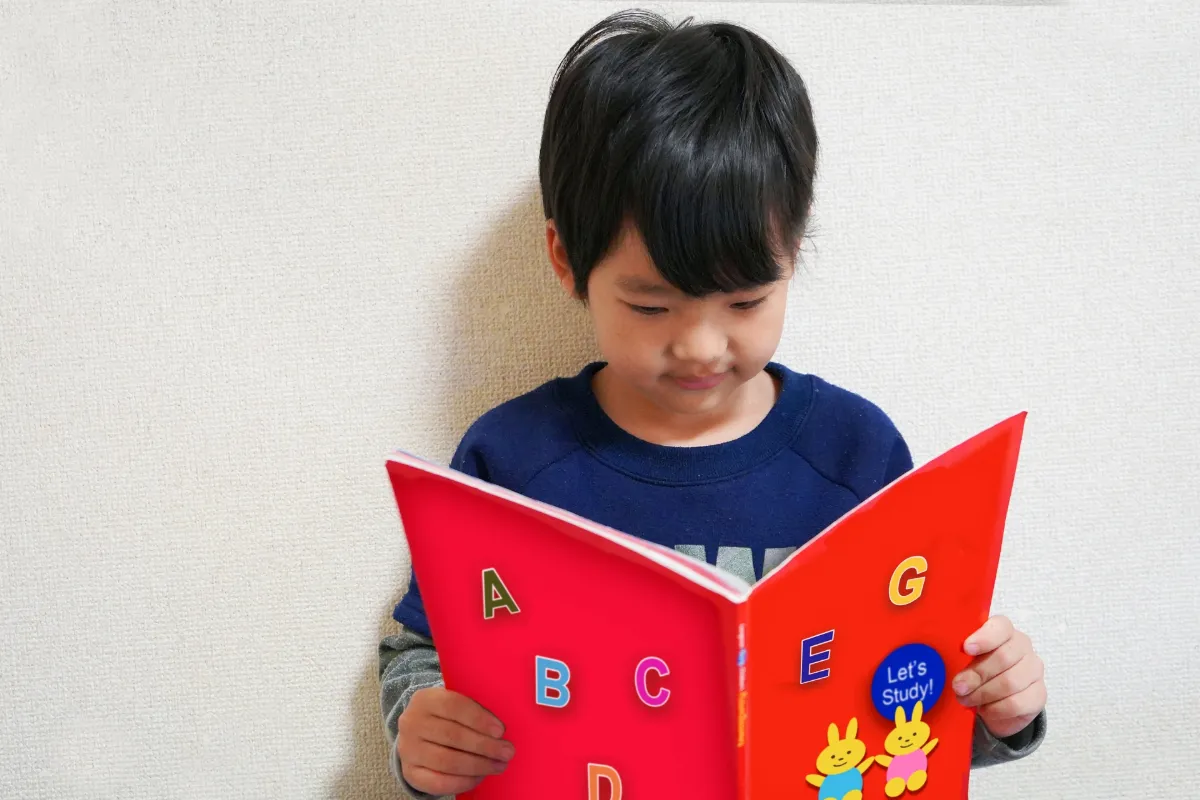年長でのタブレット学習がうまくいかなかった理由とは?
タブレット学習は手軽に始められ、楽しく学べるイメージがありますが、実際に取り組んでみて「うちの子には合わなかった」「思ったより続かなかった」と感じた家庭も少なくありません。特に年長の時期は、まだ集中力や学習の習慣が安定していないこともあり、失敗につながるケースがあります。
続かなかった理由の一例
多くの保護者が共通して語るのが、「最初は楽しそうに使っていたけれど、すぐ飽きてしまった」というものです。タブレットの画面に慣れてしまい、学習というよりはゲーム感覚になってしまったという声も見られました。
また、「操作が難しかった」「親の手助けが思った以上に必要だった」という点も、年長児には大きな壁になることがあります。
主なつまずきポイント
- 自分でアプリを操作するのが難しい
- 文字入力がスムーズにできない
- ゲーム感覚で遊んでしまい、学習に集中できない
- 内容が難しすぎて、やる気をなくしてしまう
年齢に合った設計でないと失敗しやすい
年長の子どもは、まだ「ひらがな」「数字」に慣れている段階であり、操作性や画面構成が年齢に適していないと、ただの“画面をタップするだけ”の作業になりがちです。
また、親が「ひとりで学んでくれるだろう」と期待して導入した場合、実際には親のサポートが必要で「思ったより負担だった」と感じるケースも多く見受けられました。
保護者のリアルな声
- 「最初はすごく楽しく取り組んでいたけど、1週間も経たないうちに飽きてしまった」
- 「自動読み上げがあるけど、内容を理解していないことに後から気づいた」
- 「タブレットを使わせたくて始めたけど、YouTubeやゲームの誘惑が強すぎた」
年長児にとっての「タブレット学習」は、内容やタイミングを間違えると、学びではなく“おもちゃ”になってしまう危険性もあるのです。

次の章では、実際の体験談から見えてきた失敗の実例を紹介します。
スマイルゼミ・Z会の体験談から見る失敗の実例
タブレット学習の代表格ともいえる「スマイルゼミ」や「Z会」は、年長コースも用意されており、多くの家庭で導入されています。 しかし、実際には「うまくいかなかった」「想像と違った」という体験談も少なくありません。
スマイルゼミでの失敗体験
ケース1:遊び感覚が強く、学習にならなかった
「タブレットで学ぶ=楽しい」と思って始めたものの、 ゲーム感覚で操作することに夢中になってしまい、肝心の内容が頭に入っていなかったというケースです。
保護者の声 – 「スタンプやごほうびがうれしくて、問題をすばやく終わらせようとするだけだった」 – 「内容を飛ばして、結果だけ見て『できた』気になっていた」
ケース2:親のサポートが必須で思ったより大変だった
「自分で学習してくれると思ったのに、結局隣で教えながらじゃないと進まなかった」という声も多く聞かれました。
保護者の声 – 「問題の意味を理解できずに止まってしまうので、つきっきりで見る必要があった」 – 「一人で取り組むのはまだ難しい年齢だったと感じた」
Z会での失敗体験
ケース1:教材が難しく感じた
Z会は内容の質が高い一方で、年長児にとっては少し難しいと感じることもあります。 特に初めて学習教材に触れる場合、「分からない」「面白くない」と感じやすくなります。
保護者の声 – 「問題の説明が丁寧すぎて逆に長く、集中力が続かなかった」 – 「言葉の意味が難しくて、親がその都度フォローしなければならなかった」

ケース2:紙の教材と併用が面倒だった
Z会はデジタルと紙教材を組み合わせているため、「管理が面倒」「どれをやるべきか子どもが混乱する」という声も。
保護者の声 – 「今日は紙なのか、タブレットなのか分からず、やる気をなくしていた」 – 「教材が多くて、親も把握するのが大変だった」
体験談から見えてくる共通点
- 年長児は「楽しさ重視」で始めるが、継続が難しい
- 一人で取り組むにはサポートが必要
- 内容が難しすぎるとすぐに興味を失う
- 親が期待するほど“自動的に学んでくれる”教材ではない
これらの体験談を踏まえ、次の章では「タブレット学習のメリットとデメリット」を改めて比較していきます。
タブレット学習のメリットとデメリットを比較
年長から始めるタブレット学習は、うまく活用すれば非常に効果的です。 ただし、メリットとデメリットをきちんと理解してから導入することが大切です。
メリット
| メリット | 内容 |
|---|---|
| 視覚・音声で学べる | アニメーションや読み上げ機能で理解しやすい |
| 自宅で手軽に学べる | 通塾の手間がなく、空いた時間でできる |
| ごほうび機能でやる気アップ | スタンプ・ゲーム要素で楽しみながら続けられる |
| 成績や進捗が記録される | 親が進み具合を把握しやすい |
デメリット
| デメリット | 内容 |
|---|---|
| ゲーム感覚が強すぎる | 本来の学習目的からズレやすい |
| 集中力が続きにくい | 飽きやすく、継続しづらい |
| ひとり学習に限界がある | 親のフォローが思った以上に必要 |
| 内容が年齢に合わないことも | 難易度が高いと、やる気を失う原因になる |
判断ポイント
- 「一人でやってくれる」ことを過度に期待しない
- 親も一緒に取り組む覚悟が必要
- 内容が簡単すぎず難しすぎず、子どもに合っているかを確認する
次の章では、タブレット学習で失敗しないための選び方について詳しく紹介します。
タブレット学習で失敗しないための選び方
タブレット学習の失敗を防ぐためには、導入前のチェックと事前準備が大切です。以下のポイントを確認しましょう。
1. 無料体験で子どもとの相性をチェック
スマイルゼミやZ会などは、無料体験やお試し版が用意されています。 まずは体験してみて、子どもが楽しめそうか、続けられそうかを見極めましょう。
チェックポイント – 操作しやすいか – 内容に興味を持っているか – どのくらい集中して取り組めるか
2. 親の関わりがどの程度必要かを把握する
タブレット学習は、「親の手がかからない」と思われがちですが、実際は違います。 最初は一緒に取り組むことで、子どもも安心して学べるようになります。
3. 教材の難易度と内容を確認する
内容が子どもの発達段階に合っているかどうかも重要です。 無理なく進められるレベルかどうか、デモ画面や体験版でチェックしましょう。
4. 継続できる環境づくりを整える
毎日続けるには、無理のないスケジュールを組むことが大切です。 学習の時間を決めたり、リマインダーを活用するなどして、生活の中に習慣化させましょう。
タブレット学習が合わない子に向いている学習法とは?
タブレット学習がうまくいかなかった場合、他の方法で学習習慣を身につけることも可能です。
1. 紙のワーク教材
ひらがな・数字・迷路・点つなぎなど、手を動かして学べる教材は、年長児にとって分かりやすく親しみやすいです。
2. 学習ポスター・貼る教材
部屋に貼って視覚から学べる教材もおすすめです。毎日目にすることで自然と覚える習慣がつきます。
3. 知育玩具や遊びの中で学ぶ
学習にとらわれず、遊びの中で知識や思考力を育てる方法も有効です。
例 – ブロック遊び → 図形認識・論理的思考 – 絵本の読み聞かせ → 言葉や感情の理解 – ごっこ遊び → 社会性・コミュニケーション力
まとめ
年長からのタブレット学習は、メリットも多い一方で「合わなかった」という体験談も数多くあります。 失敗しないためには以下の点を意識しましょう。
- まずは無料体験で相性を確認する
- 内容の難易度や使いやすさをチェックする
- 親の関わりを前提に導入する
- うまくいかない場合は、紙教材や遊びを取り入れる
子どもにとって「学ぶことが楽しい」と感じられる方法を見つけることが、何よりも大切です。