子どものタブレット利用時間はどれくらいが適切?
タブレットを活用した学習や知育はとても便利ですが、「一体どのくらいの時間まで使わせていいの?」と悩むご家庭も多いですよね。 実際、タブレット利用時間(スクリーンタイム)については、国内外の専門機関でも推奨時間が示されています。

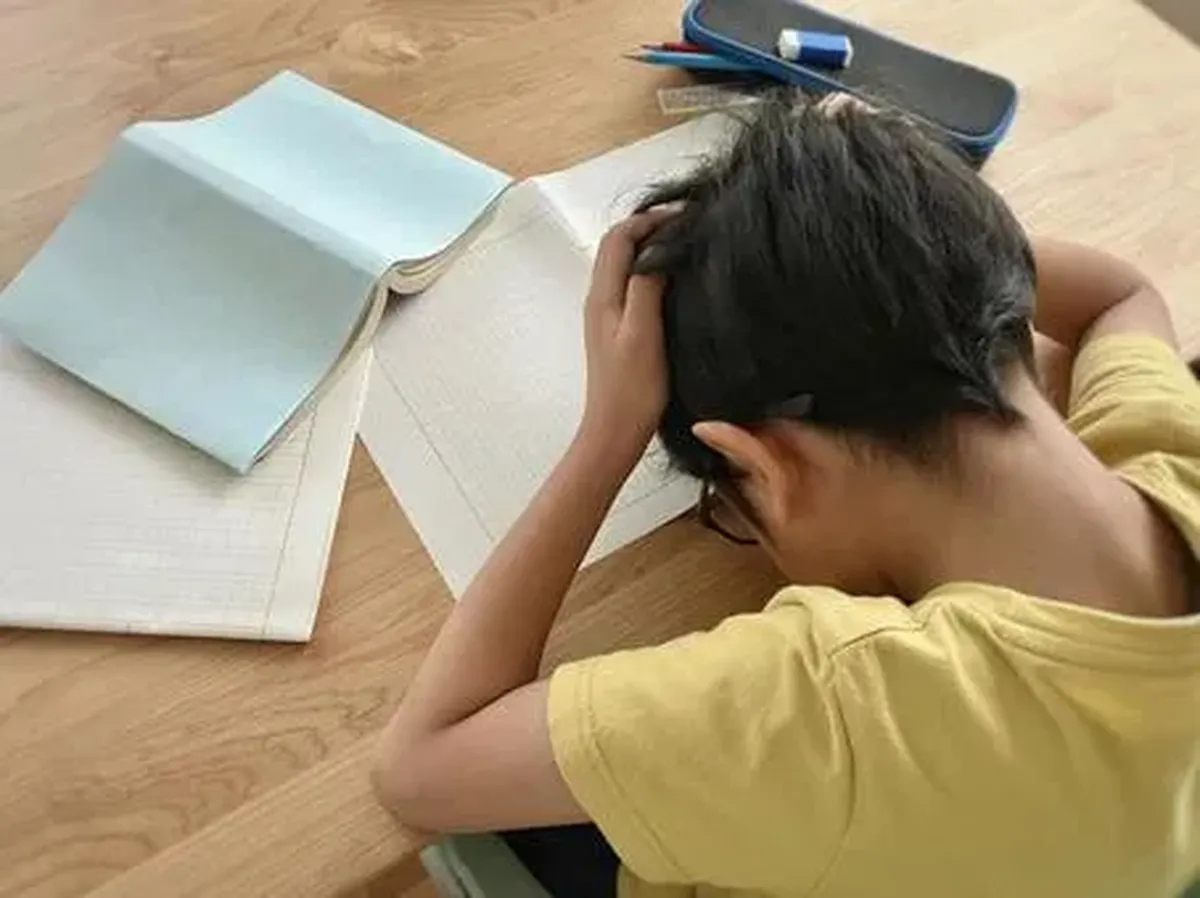
スクリーンタイムの目安(日本小児科学会などの提言)
| 年齢 | 推奨される1日のスクリーンタイム |
|---|---|
| 2歳未満 | 使用は推奨されない(画面との接触は最小限に) |
| 2~5歳 | 1時間以内(保護者と一緒に内容を選ぶこと) |
| 小学生 | 1~2時間以内(学習目的含むが休憩をはさむこと) |
なぜ時間制限が必要なのか?
タブレットは魅力的なツールですが、無制限に使っているとさまざまな問題が起こる可能性があります。
- 視力や姿勢への悪影響
- 夜の睡眠リズムが崩れる
- 外遊びや対人関係の時間が減る
- 依存傾向が生まれやすい
タブレットを「便利な学習ツール」として活用するためには、年齢に応じた使用時間と、正しい使い方を家族で共有しておくことが大切です。
次の章では、長時間使用による具体的なリスクについて詳しく解説します。
長時間使用による影響とスクリーンタイムのリスク
タブレットは学習や遊びに使える便利なツールですが、長時間の使用にはリスクが伴います。特に成長期の子どもにとって、タブレットの使いすぎは身体的・心理的な影響を及ぼすことがあります。
1. 視力への悪影響
タブレットを長時間見ることで、ピント調節がうまくできなくなり、近視が進行する恐れがあります。 特に子どもは「疲れた」「見づらい」と感じにくく、知らず知らずのうちに目に負担がかかっていることも。
対策: – 30分使用したら5?10分休憩する – 部屋を明るくして使用する – 画面と目の距離を30cm以上あける
2. 睡眠の質が低下する
就寝前のタブレット使用は、ブルーライトの影響で睡眠の質が悪くなるといわれています。 夜遅くまで画面を見ていると、寝つきが悪くなったり、睡眠時間が短くなる原因になります。
対策: – 就寝1時間前には使用をやめる – 寝室にはタブレットを持ち込まない – 夜はリラックスできる読書や会話の時間に切り替える
3. コミュニケーション不足
タブレットばかりに集中してしまうと、家族との会話や友達との関わりが減り、社会性の発達が遅れることもあります。
対策: – 家族と使い方について話し合う – ルールを親子で一緒に決める – 親もタブレットを一緒に使い、学習内容を共有する
4. 自己管理が難しい
まだ自己コントロール力が育っていない年齢では、「あと5分」が守れないこともしばしば。時間制限をしないと、どんどん使う時間が長くなってしまいます。
次の章では、家庭で実践できる「時間制限ルール」とその成功例をご紹介します。
各家庭での時間制限ルールと成功例
タブレットの使用時間に関するルールは、家庭ごとに異なります。しかし、「わが家のルール」がしっかり決まっている家庭ほど、子どもが安心してタブレットと付き合えている傾向があります。
実際に行われているルールの例
全国の保護者を対象に行われたアンケートでは、以下のようなルールが多く挙げられていました。
| ルールの内容 | 実践している家庭の割合(参考) |
|---|---|
| 平日は1日30分まで | 約40% |
| ご飯の前後は使わない | 約35% |
| 就寝前1時間は使用禁止 | 約30% |
| 使う時間をタイマーで管理 | 約25% |
成功例1:タイマーで「見える化」
「あと何分か」を子ども自身が把握できるよう、キッチンタイマーやアプリのタイマー機能を活用する家庭が増えています。 終了の時間が視覚化されていることで、親子の言い争いが減ったという声も。
成功例2:「ごほうび」ではなく「自立」を目指す
「30分やったらお菓子をあげる」というごほうび制度ではなく、時間を守れたこと自体を褒めるスタイルが有効です。
- 「今日は時間守れたね、かっこよかったよ!」
- 「時間通りに終われるって、すごいね」
こうした声かけを続けることで、子ども自身が「自分で管理すること」の大切さを学びやすくなります。
成功例3:使う時間帯を限定する
- 朝は使わず、夕食後の30分だけ
- 週末だけは1時間OK
- 宿題が終わってからにする
など、ルールを状況に合わせてカスタマイズすることで、家庭内のストレスが軽減されたという実例もあります。
次の章では、時間制限を手助けしてくれる「ペアレンタルコントロール機能」やおすすめのアプリをご紹介します。
ペアレンタルコントロールとおすすめ制限アプリ
家庭でタブレットの時間制限をしようと思っても、毎回親が声をかけたり管理するのは大変ですよね。 そんなときに役立つのが「ペアレンタルコントロール機能」や、専用の時間制限アプリです。
タブレット本体にある制限機能(無料)
1. iPad(iOS)の「スクリーンタイム」機能
- アプリごとの使用時間を制限
- 使用可能時間帯の設定
- パスコードでロック
- 利用状況のレポート表示
2. Androidの「デジタルウェルビーイング」
- 1日あたりの利用時間設定
- アプリのタイマー
- ナイトモード(ブルーライト軽減)
専用のペアレンタルアプリも便利
| アプリ名 | 特徴 |
|---|---|
| Google ファミリーリンク | Androidユーザー向け。端末の遠隔管理や時間制限ができる。 |
| Airdroid Parental Control | iOS・Android両対応。位置情報やアプリ使用状況も確認可。 |
| Famisafe | スケジュール制限、危険ワードの検知など機能が豊富。 |
アプリ活用のメリット
- 毎日の管理がラクになる
- 使用状況がグラフで見える
- 外出中でも遠隔で制限可能
- 子どもにルールを説明しやすい
ただし、制限アプリに頼りすぎるのではなく、子ども自身がルールを理解し、納得して使うことが大切です。
次の章では、親が無理なく続けられ、子どもも納得してくれる「時間制限の工夫」をご紹介します。
子どもが納得して守れる時間制限の工夫とは?
「何度注意してもやめない」「あと5分が守れない」 こんなお悩みは、多くの親御さんが感じるもの。でも、子どもが自分で納得してルールを守れるようにするためには、ちょっとした工夫がカギになります。
1. ルールは親子で一緒に決める
時間制限のルールを大人が一方的に押しつけてしまうと、子どもは「守らされている」と感じて反発しやすくなります。
実践ポイント: – 「何分ならできそう?」と子どもに相談する – ルールは紙に書いて見える場所に貼る – ルールを守れたら、自然に褒める・共感する
2. タイマーを子ども自身にセットさせる
時間の意識を育てるには、子どもが「自分で」タイマーをセットするのが効果的です。 終了時間を自分で決めることで、納得感が生まれやすくなります。
3. 終了後の「次の行動」を決めておく
タブレットをやめたあと、何をするかが決まっていないと、ダラダラと再開してしまいがちです。
例: – 「タブレットが終わったらおやつにしよう」 – 「30分やったら、絵本読もうね」 – 「終わったらブロック遊びしようか」
楽しい予定を用意しておくことで、「終わるのがイヤ」が軽減されます。
4. 子どもによってルールを柔軟に変える
きょうだいや年齢によって、同じルールが合うとは限りません。 学年や性格に応じてルールを調整し、「あなたに合わせたルールだよ」と伝えると、より納得しやすくなります。
5. 親もルールを守る姿勢を見せる
親がスマホをダラダラ使っていたら、子どもが納得してやめるのは難しいですよね。 「ママも時間を決めてるよ」といった姿勢を見せることで、子どもは自然とルールを受け入れやすくなります。
まとめ
タブレットは便利な学習・遊びのツールですが、適切な時間制限がなければ、心身への悪影響を及ぼすこともあります。
- 年齢に応じたスクリーンタイムの目安を意識する
- 長時間使用によるリスク(視力低下・睡眠障害・依存)に注意する
- 親子で納得できるルールを作り、無理なく続ける工夫をする
- タイマーや制限アプリを活用して、家庭での管理負担を減らす
- 最も大切なのは「子ども自身が納得して守れる環境」をつくること
無理なく、でもしっかりと。家族に合った方法で、タブレットとの上手な付き合い方を見つけていきましょう。


