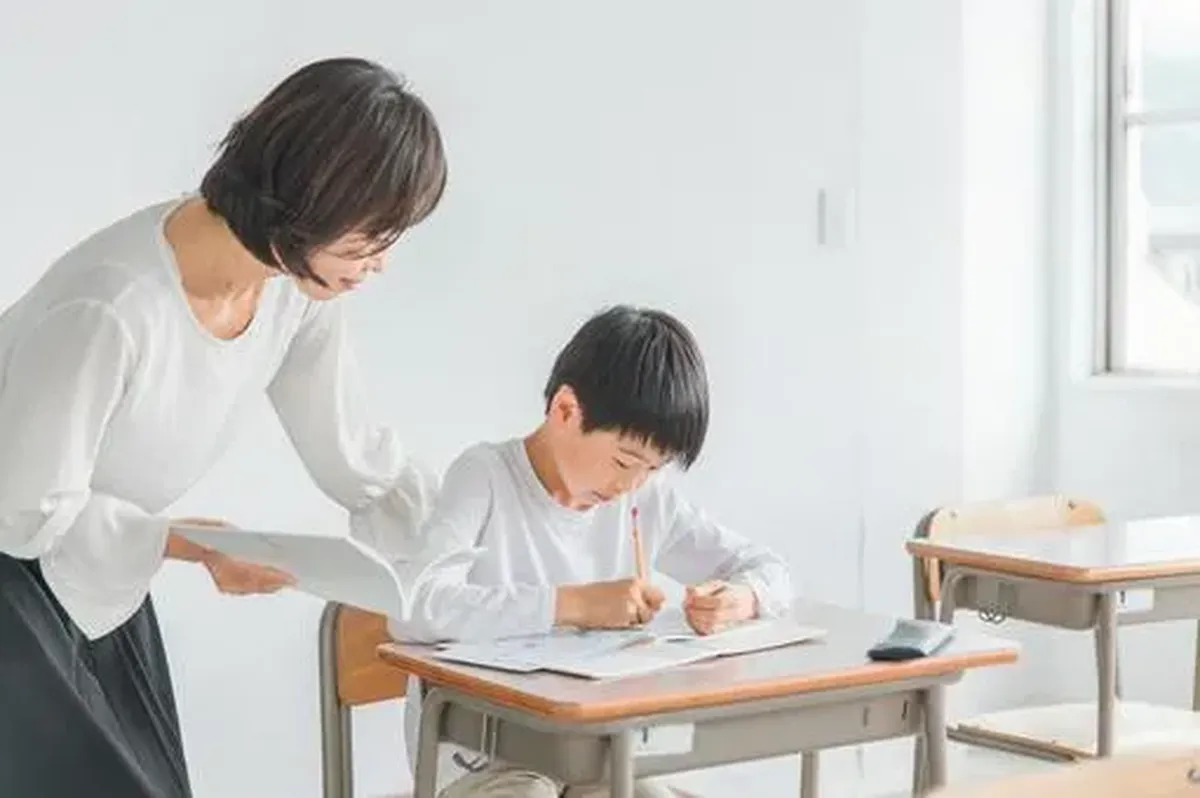小学校の授業についていけない…よくあるつまずきとその背景
小学校に入学して間もない時期は、子どもも親も「授業についていけているかな?」と不安になることが多いですよね。特に低学年のうちは、集団生活や教科の勉強に慣れるまでに個人差が大きく出やすいものです。
よくあるつまずきのパターン
| 教科 | つまずきやすい内容 |
|---|---|
| 算数 | 数の概念、繰り上がり・繰り下がり、図形の理解 |
| 国語 | 読み書きの定着、文章の意味をとらえる力 |
| 授業全体 | 黙って話を聞く、黒板をノートに写す、指示を理解する |
このような「基本の動作」が難しいと、勉強内容以前に授業自体についていけないと感じることがあります。
つまずきの背景にあること
-
生活習慣の違い
朝起きる時間、食事のタイミングなど、生活リズムが整っていないと集中力に影響が出やすくなります。 -
学びのスタート地点の違い
ひらがなが書ける・時計が読めるなど、入学時点でのスキル差は非常に大きいです。 -
性格や個性
大人しくて自分から質問できない子、集中力が短い子など、それぞれの性格によって「授業への入り込みやすさ」も異なります。
生活習慣の違い 朝起きる時間、食事のタイミングなど、生活リズムが整っていないと集中力に影響が出やすくなります。
学びのスタート地点の違い ひらがなが書ける・時計が読めるなど、入学時点でのスキル差は非常に大きいです。
性格や個性 大人しくて自分から質問できない子、集中力が短い子など、それぞれの性格によって「授業への入り込みやすさ」も異なります。
「うちの子だけがついていけないのでは…」と感じるかもしれませんが、実は多くの子が一度はこうした壁にぶつかります。 次の章では、授業についていけない子どもが見せるサインや原因を詳しく見ていきましょう。
子どもが授業についていけない原因とは?見逃しがちなサイン
子どもが「学校で困っている」とはっきり言ってくれれば分かりやすいのですが、実際には言葉にしないままモヤモヤを抱えていることが多いものです。 ここでは、授業についていけない子どもが出すサインや、考えられる原因を解説します。
見逃しがちな“ついていけていない”サイン
| サイン | 親が気づきやすい行動例 |
|---|---|
| 学校の話をしなくなる | 「今日どうだった?」と聞いても「別に…」と曖昧な返事が増える |
| 朝の登校を渋るようになる | 理由も言わず「行きたくない」が増える |
| 宿題を嫌がる・先延ばしにする | 宿題を見ると泣いたり怒ったりする |
| 勉強に自信をなくしている | 「ぼくバカだから…」など否定的な言葉を言い出す |
授業についていけない原因
-
理解するスピードの個人差
低学年では特に、同じ内容を学んでも理解に時間がかかる子とすぐに吸収できる子の差が大きく出ます。 -
集中力や記憶力の特性
集中できる時間が短かったり、一度聞いたことをすぐに忘れてしまうことが原因になることもあります。 -
黒板や指示の理解が苦手
視覚・聴覚的な情報処理に苦手さがある場合、黒板を写す、先生の話を理解するなどの基本的な作業が難しいことがあります。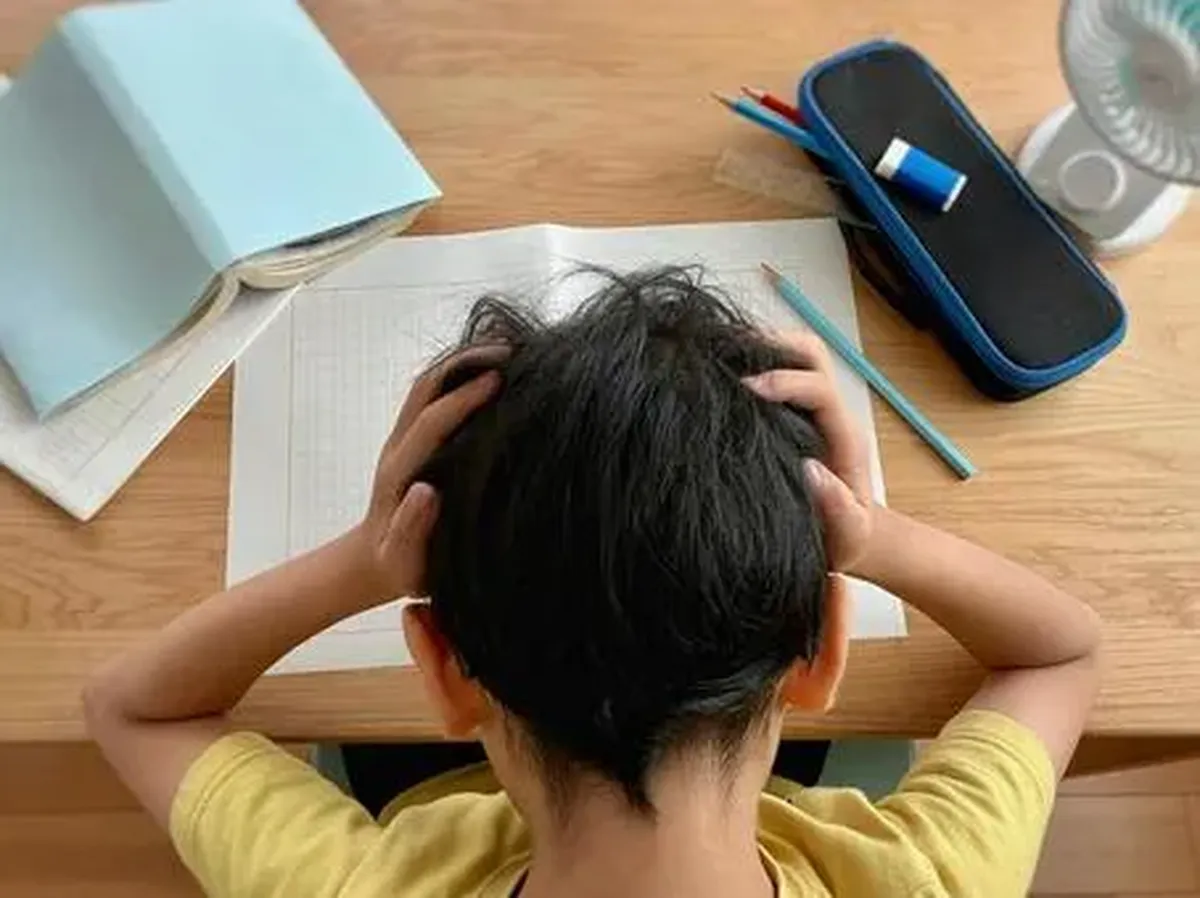
-
発達特性や学習障害(LD)などの可能性
発達に偏りがある子どもは、学習内容よりも「学び方」そのものが合っていないケースもあります。必要に応じて専門機関のサポートを受けることが大切です。
理解するスピードの個人差 低学年では特に、同じ内容を学んでも理解に時間がかかる子とすぐに吸収できる子の差が大きく出ます。
集中力や記憶力の特性 集中できる時間が短かったり、一度聞いたことをすぐに忘れてしまうことが原因になることもあります。
黒板や指示の理解が苦手 視覚・聴覚的な情報処理に苦手さがある場合、黒板を写す、先生の話を理解するなどの基本的な作業が難しいことがあります。
発達特性や学習障害(LD)などの可能性 発達に偏りがある子どもは、学習内容よりも「学び方」そのものが合っていないケースもあります。必要に応じて専門機関のサポートを受けることが大切です。
子ども自身が困っていることに気づくためには、日常のちょっとした変化に親が気づいてあげることが何より大切です。
次の章では、子どもが「授業についていけない」と感じているときに、親が避けるべき対応についてご紹介します。
親が焦る前に!やってはいけない3つの対応とは
「授業についていけないかもしれない…」と不安を感じたとき、親としてすぐに何か行動したくなるのは自然なことです。 でも、その“焦り”からくる対応が、かえって子どもの自信を奪ってしまうこともあります。

ここでは、子どもが授業についていけないときに、親がついやってしまいがちなNG行動とその代替案をご紹介します。
1. 叱って無理にやらせる
「どうしてこんな問題もできないの!」「ちゃんと授業聞いてるの?」 そんな言葉は、子どもにとってはプレッシャーでしかありません。
代わりにすべき対応: 「難しかったね」「どこが分からなかった?」と共感しながら寄り添い、子ども自身が「できた」と感じられるようなサポートをしましょう。
2. 他の子と比べる
「○○ちゃんはもう読めるのに…」「お兄ちゃんの時はできたのに…」 比べられることで、自信をなくし、やる気も失われてしまいます。
代替案: その子の“昨日の自分”と比べて、少しでも成長した点を見つけてあげましょう。
3. すぐに「習い事」で補おうとする
塾や通信教育に通わせるのは有効な手段ですが、「今すぐやらせなきゃ!」と焦って始めても、子どもの負担が増えるだけになることも。
代替案: まずは家庭でできる簡単なサポートから始め、子どもが「できるようになりたい」と思えるようになるのを待ちましょう。
子どもにとっては、「親が信じてくれている」という気持ちが一番の支えになります。
次の章では、家庭でできる授業サポートの方法を具体的にご紹介していきます。
授業についていけない子どもを支える家庭での学習サポート
子どもが「授業についていけない」と感じているとき、家庭でできるサポートがあると安心感につながり、少しずつ自信を取り戻せるようになります。 ここでは、無理なく取り組める家庭学習の工夫をご紹介します。
1. 苦手な教科を「遊び」で補う
- 算数が苦手なら、ブロックや買い物ごっこで数を扱う
- ひらがなが苦手なら、絵本を一緒に音読したり、文字カードで遊ぶ
勉強=机に向かうことという固定観念を取り払い、生活の中に楽しく学べる仕掛けを取り入れましょう。
2. 1日5?10分の「できた体験」を積み重ねる
最初からたくさんの時間をかける必要はありません。 「昨日より1問多く解けた」「自分で読めた!」という小さな成功体験の積み重ねが、次のやる気につながります。
3. リラックスした環境づくり
- 勉強の前に一緒に深呼吸する
- 時間を決めて、ダラダラせずに取り組む
- 終わったあとは必ず「ありがとう」「頑張ったね」と声をかける
学習の効果は「気持ち」に大きく左右されます。安心して取り組める空気づくりが、成果以上に大切です。
4. 親が「見てるよ」と伝える
子どもは「誰かが見てくれている」と感じるだけで、安心して挑戦できるようになります。 たとえ隣で見ていなくても、「あとで見せてね」と声をかけるだけでも十分効果があります。
5. 「家庭だけで抱えない」ことも大切
頑張っても解決しない場合や、親子関係がぎくしゃくし始めた場合は、外部の力を借りることも必要です。
次の章では、学校や専門機関に相談するタイミングや方法について詳しくご紹介します。
担任や専門機関への相談はいつ・どうする?適切なタイミングと方法
「もしかしたら授業についていけていないかも…」と感じたとき、家庭だけで抱え込まず、学校や専門機関に相談することはとても大切です。 ここでは、相談すべきタイミングと、効果的な伝え方のポイントをご紹介します。
担任の先生に相談すべきタイミング
以下のような変化が見られたら、早めの相談がおすすめです。
| 状況 | 具体例 |
|---|---|
| 学校の話を避けるようになった | 「今日どうだった?」と聞いても無言や否定的な返事が多い |
| 宿題に極端な拒否反応を示す | 「やりたくない」「わからない」と毎日のように嫌がる |
| 学校に行きたくない様子が見られる | 朝になるとお腹が痛い、頭が痛いと言い出すことが増える |
| 家庭学習でも理解が難しそう | 教科書やプリントを見ても、内容が定着していない |
担任への相談のポイント
- 事実を丁寧に伝える:「宿題をやりたがらない」「音読でつまずいている」など具体的なエピソードを添えると◎
- 協力をお願いする姿勢:「何か家庭でできることはありますか?」と聞くことで、建設的なやり取りになりやすい
- 相談のタイミングは短時間でもOK:連絡帳や面談、放課後の5分など、無理なく相談できる手段を選びましょう
専門機関に相談するケース
以下のようなケースでは、教育相談センターや発達支援機関などの活用を検討しましょう。
- 何度教えても基本的な理解が難しい
- 先生からも「様子を見ましょう」と言われ続けているが改善が見られない
- 発達の偏りや特性があるかもしれないという不安がある
自治体の子育て支援センターや教育委員会の窓口などで、無料で相談できるサービスもあります。
大切なのは「ひとりで抱え込まないこと」
親としては「もう少し様子を見よう」「自分の教え方が悪いのかも…」と悩みがちですが、早めの相談は子どもにとっても安心材料になります。
信頼できる大人がそばにいるということが、何よりの支えになるのです。
まとめ
小学校で「授業についていけないかもしれない」と感じたとき、大切なのは焦らずに原因を見つめ、できるサポートを一つずつ積み重ねていくことです。
- 低学年では「ついていけない」の感じ方に大きな個人差がある
- 子どもが出す小さなサインに気づくことが第一歩
- 叱る・比べるよりも、共感しながら支える姿勢が大切
- 家庭でのサポートは「遊び感覚」と「成功体験」を意識して
- 必要なら早めに担任や専門機関に相談を
子どもの成長には「今できない」があって当然。 その時期に、安心して「わからない」を伝えられる環境こそが、学びへの第一歩になります。