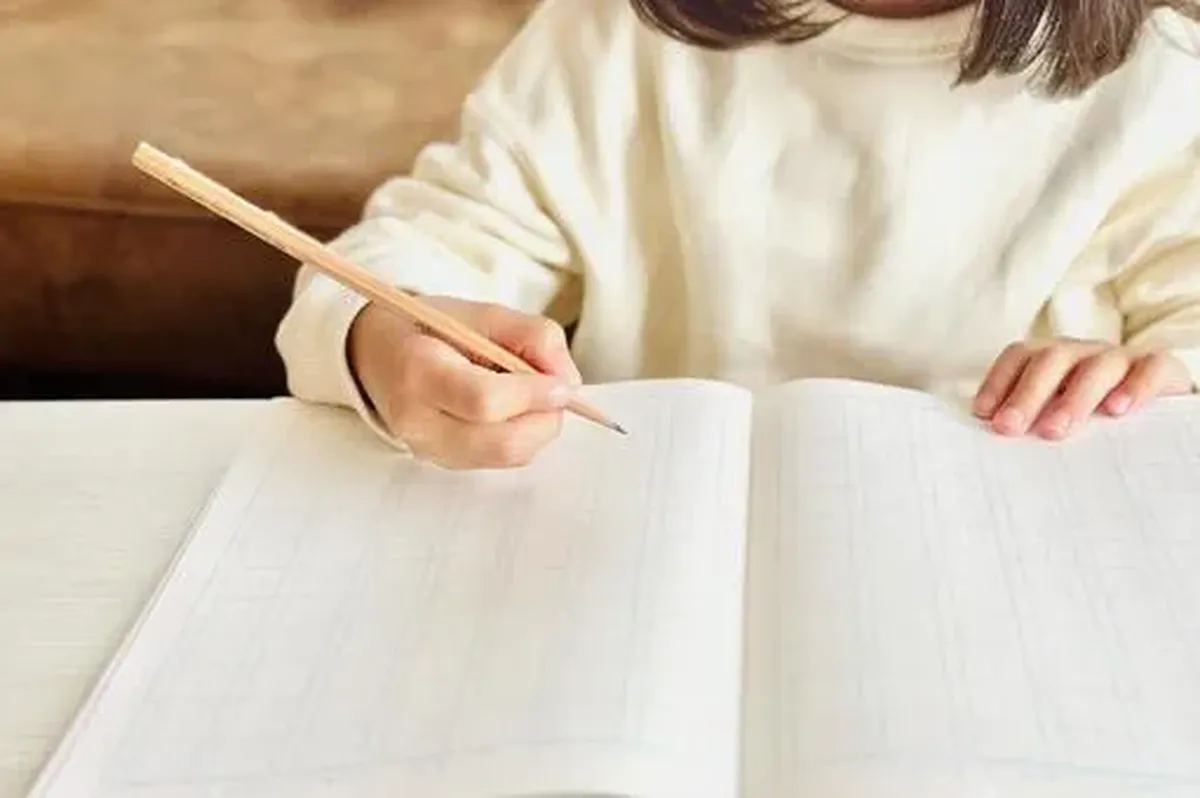幼児期に思いやりの心が育つ理由とその重要性
「人にやさしくできる子に育ってほしい」?? これは多くの保護者が共通して願うことではないでしょうか? その“やさしさ”や“思いやりの心”は、幼児期から自然に育まれていくと言われています。
ではなぜ、幼児期が思いやりの芽生えに大切な時期なのか。その理由と育む意味についてお話しします。
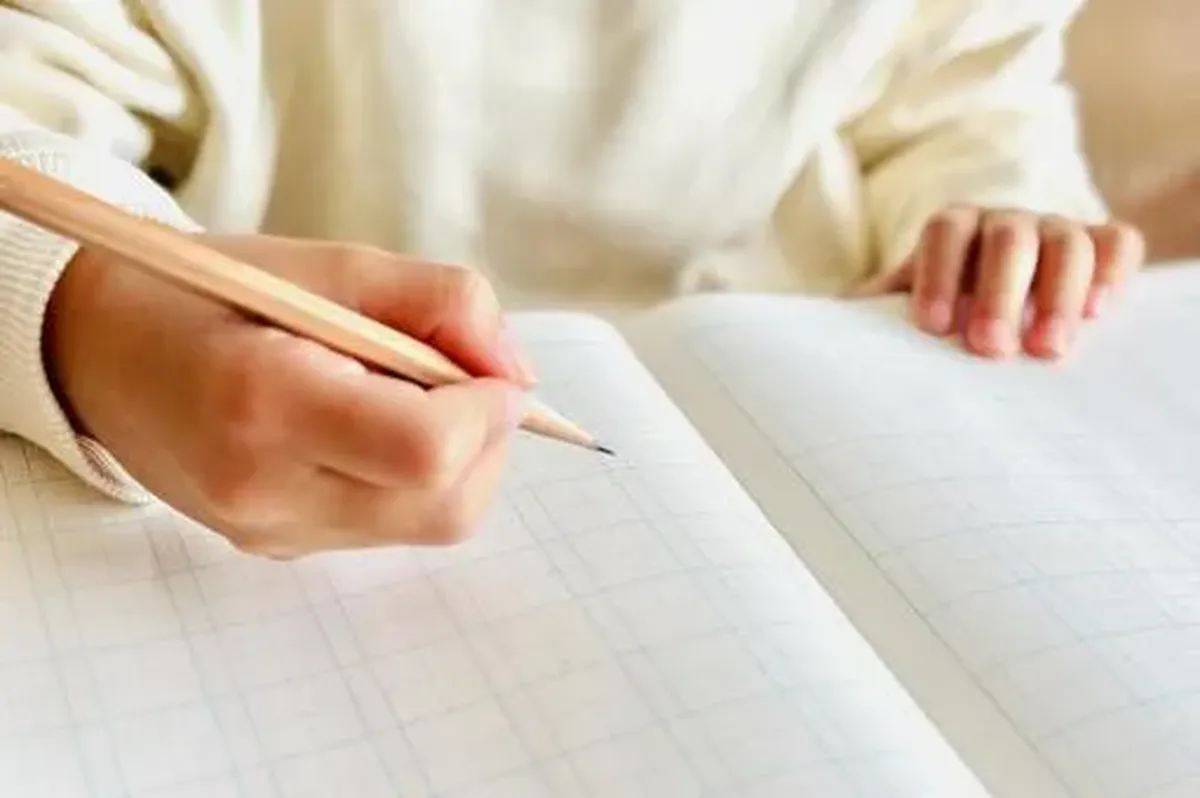
幼児期は「共感力」の土台が育つ時期
思いやりの原点は、相手の気持ちに気づく「共感力」です。 幼児期は、他者との関わりが増える中で、「悲しそう」「楽しそう」といった感情を少しずつ理解できるようになります。
| 発達段階 | 見られる共感のサイン |
|---|---|
| 2~3歳 | 泣いている子に近づく、まねをするなど感情の模倣 |
| 4~5歳 | 「○○ちゃんが悲しいって言ってた」と他者の感情を言葉にできる |
| 5~6歳 | 「どうすれば喜ぶかな?」と相手の立場を考えた行動が取れるように |
思いやりは“教える”より“育まれる”もの
思いやりは、テストで測れるものではなく、「目には見えにくい心の力(非認知能力)」のひとつです。 それは、大人からの教え込みではなく、身の回りの体験や関わりの中で“感じること”を通して育っていくもの。
そのためには、
- 安心できる家庭環境
- 親からのあたたかい言葉や表情
- 相手とのやりとりを経験する機会
がとても重要になります。
思いやりが育つと、将来こんな力に
- 自己肯定感が高くなる
- トラブルに巻き込まれにくくなる(いじめ・孤立の予防)
- 協調性・社会性が身につき、人間関係がスムーズになる
- 学校や社会での適応力が高まる
思いやりは、子ども自身が生きやすくなるための“生きる力”の一部なのです。

思いやりは、小さな「気づき」や「ありがとう」のやりとりの中で、少しずつ育っていきます。 この大切な時期に、「感じる心」をゆっくり丁寧に育んでいきたいですね。
思いやりを育てるための親の関わり方と声かけ例
子どもの思いやりの心を育てるには、日々の親の関わり方が大きなカギを握っています。 「こうしなさい」と言葉で教えるよりも、親のふとした態度や言葉から、子どもは“やさしさ”を感じ取っていくのです。
ここでは、家庭でできる具体的な接し方や、思いやりを引き出す声かけのヒントをご紹介します。
思いやりを育てる“親の姿勢”とは?
| 親の行動 | 子どもが受け取るメッセージ |
|---|---|
| 子どもの気持ちに共感する | 「気持ちをわかってもらえるってうれしい」 |
| 困っている人に手を差し伸べる | 「人が困っていたら助けていいんだ」 |
| 「ありがとう」「ごめんね」を日常的に使う | 「気持ちは言葉で伝えることが大事なんだ」 |
子どもは、親の言葉や行動を“まねる”ことで社会性を身につけていきます。 思いやりも例外ではなく、親の姿そのものが最高のお手本になるのです。
思いやりを引き出す声かけの例
- 「○○ちゃん、泣いてたね。どうしたのかな?」
- 「おもちゃ、貸してくれてうれしかったね。今度は○○も貸してあげようね」
- 「ママも疲れてたけど、○○が“おてつだいする!”って言ってくれて元気が出たよ」
- 「それ、すごくやさしい気持ちだね。○○って本当にあたたかい子だね」
大切なのは、「相手の気持ちに気づけたこと」「やさしい行動をしたこと」を、すぐその場で具体的にほめてあげること。
やってしまいがちなNGな声かけに注意
| NGな例 | 子どもへの影響 |
|---|---|
| 「なんで貸してあげないの?」 | 自分の気持ちを押し殺してしまうようになる |
| 「○○ちゃんはできてるよ」 | 比べられることで、自分に自信が持てなくなる |
| 「泣いてる子にあやまってきなさい」 | 表面的な謝罪になり、本当の気持ちが育たないことも |
思いやりは“行動”ではなく“気持ち”から育つもの。 無理やりやらせたり、他の子と比べたりせず、その子のペースで「感じる経験」を重ねられるような関わりが大切です。
子どもは、あたたかいまなざしと共感の言葉に育てられます。 親のやさしさが、子どもの思いやりの種を静かに育てていくのです。
遊びや日常の中でできる“やさしさ”の育み方
思いやりは、特別なレッスンや難しいしつけではなく、子どもの日常の中にこそ育つチャンスがいっぱいあります。 特に、遊びの中やちょっとした日常のやりとりを通して、自然と相手を思いやる心が育っていきます。
ここでは、日常生活の中で実践しやすい思いやりの育み方をご紹介します。
1. ごっこ遊びで「相手の立場」を想像する
ごっこ遊びは、思いやりの土台となる“想像力”を育てる最高の遊び。 たとえば…
- お医者さんごっこ → 「痛いところあるかな?」と相手を思いやる
- お店屋さんごっこ → 「どれが食べたいですか?」と相手に気を配る
- 赤ちゃんのお世話ごっこ → 「お腹すいたのかな?」と相手の気持ちを考える
こうしたやりとりは、遊びながら共感力を育てる大切なステップになります。
2. 絵本の読み聞かせで感情を共有する
絵本は、子どもが他者の気持ちを疑似体験できる貴重なツールです。
- 「この子、どんな気持ちだったんだろう?」
- 「○○だったらどうする?」
- 「このあと、どうなると思う?」
こうした問いかけをしながら読むことで、「感じる力」「考える力」が育ちます。
3. きょうだいや友達とのトラブルも学びのチャンスに
日常の中では、「貸してくれない」「順番が守れない」などのトラブルもよくあります。 でも、これも立派な“思いやりの学び”の機会です。
| トラブルの例 | 親の関わり方 |
|---|---|
| おもちゃを取り合った | 「○○も使いたかったよね。でもお友達も遊びたかったんだね」と両者の気持ちを言語化する |
| 友達が泣いてしまった | 「あの子、どんな気持ちだったかな?」「どうしたらよかったかな?」と一緒に考える |
4. 家庭内で“ありがとう”をたくさん使う
- ごはんを運んでくれたら「ありがとう」
- お片付けを手伝ってくれたら「助かったよ」
- ちょっとした思いやりを見せたら「○○って優しいね」
大人が率先して感謝の言葉を使うことで、子どもも自然と“やさしさの循環”を覚えていきます。
思いやりは、教え込むものではなく、「感じる・考える・まねる」中で少しずつ育っていきます。 日常の中にある小さなやさしさの芽を、たくさん見つけて、やさしく育てていきましょう。
思いやりの芽を育てた家庭の実例エピソード
子どもに思いやりを持ってほしい?? そう願う保護者の中には、「ちゃんと育っているのか不安」「具体的にどう接すればいいの?」と悩む方も多いはず。
ここでは、実際に日常の中で思いやりの芽を育んだご家庭のエピソードをご紹介します。リアルな体験談から、子どものやさしさが育つヒントを見つけてみてください。
エピソード①:弟を思いやる4歳の女の子
「2歳下の弟が泣いていたとき、『○○ちゃん、どうしたの?』と声をかけ、お気に入りのぬいぐるみをそっと渡していました。
私が『すごくやさしいね』と伝えると、ちょっと照れながらも、とても嬉しそうでした。」
「2歳下の弟が泣いていたとき、『○○ちゃん、どうしたの?』と声をかけ、お気に入りのぬいぐるみをそっと渡していました。 私が『すごくやさしいね』と伝えると、ちょっと照れながらも、とても嬉しそうでした。」
ポイント: 自然に出たやさしさを、すぐに具体的に褒めて“自信”につなげた。
エピソード②:スーパーで見せた思いやりの一言
「レジに並んでいたとき、前のおばあちゃんが荷物を落としてしまい、6歳の息子が『持ちましょうか?』と声をかけました。
周囲の人に褒められたことで、自分の行動に誇りを持ったようです。」
「レジに並んでいたとき、前のおばあちゃんが荷物を落としてしまい、6歳の息子が『持ちましょうか?』と声をかけました。 周囲の人に褒められたことで、自分の行動に誇りを持ったようです。」
ポイント: 小さな社会の中で思いやりを実践できるチャンスを逃さなかった。
エピソード③:友達に謝るのが苦手だった男の子(5歳)
「おもちゃの取り合いで友達を泣かせてしまい、なかなか謝れずにいました。
でもあとから『○○くん、悲しかったかな?』と聞くと、『うん…ごめんねって言えばよかった』とポツリ。
次に会ったとき、自然に“ごめんね”が言えました。」
「おもちゃの取り合いで友達を泣かせてしまい、なかなか謝れずにいました。 でもあとから『○○くん、悲しかったかな?』と聞くと、『うん…ごめんねって言えばよかった』とポツリ。 次に会ったとき、自然に“ごめんね”が言えました。」
ポイント: 強制ではなく、自分の気持ちで気づく機会を作ったことで、思いやりの芽が育った。
共通する“育ち方”のヒント
| 育て方の特徴 | 解説 |
|---|---|
| 行動ではなく“気持ち”に注目 | 「やさしい気持ちだったね」と内面を褒める |
| 無理にやらせない | 気持ちが動いたときにだけ自然に促す |
| 感情を共有する | 「ママもうれしかった」「その子も助かったね」など一緒に喜ぶ |
子どもが思いやりを見せたとき、それを「気づいてもらえた」「受け止めてもらえた」と感じることが、自信と自己肯定感の土台になります。
やさしい行動の背景にある“心の動き”に寄り添ってあげることが、思いやりの芽をゆっくりと確かなものへと育てていくのです。